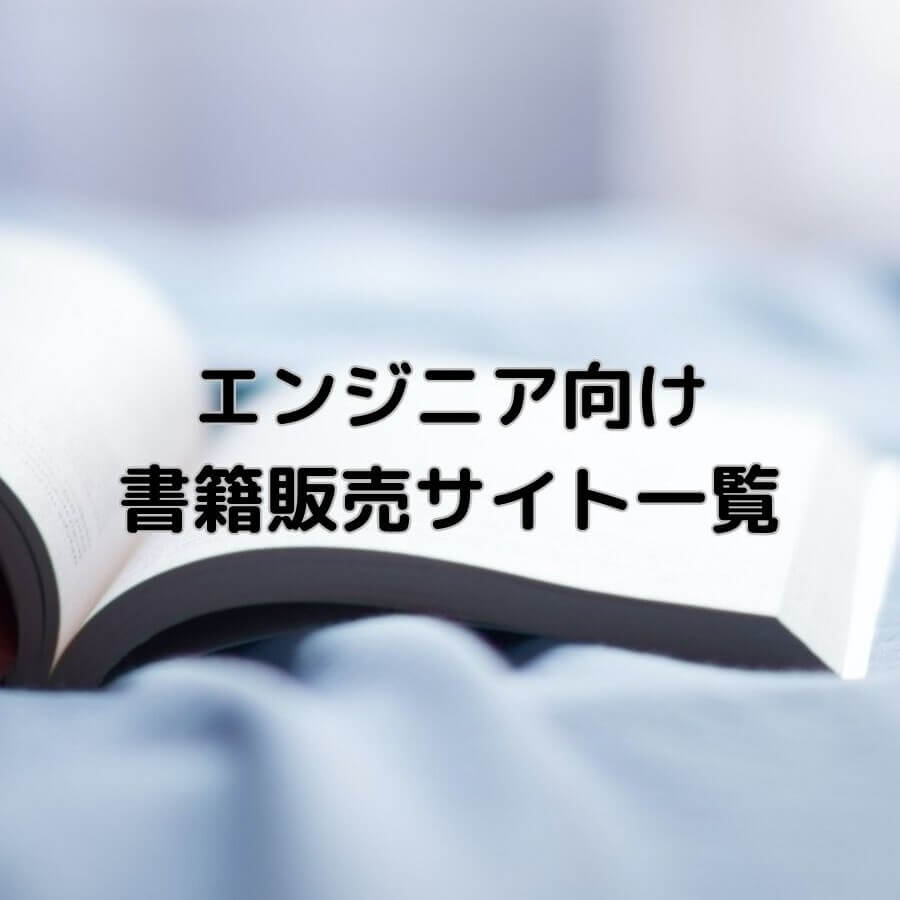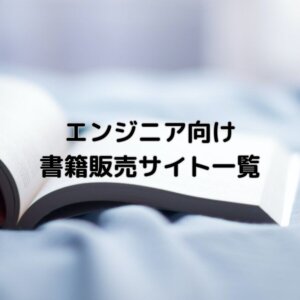取り扱い数が多い書店サイトや古本サイトへのリンクを集めてあります。
技術書を安く手に入れたい人の比較用にも便利です。
入門書など初心者用なら月980円で読み放題の 【PR】Kindle Unlimited がお得です。

Kidle本はAmazon検索で探すんだけど、人気順で表示されるから、初心者ならとりあえず上から読んでおけばOK!
探す手間が省けるのもいいところだね。
気に入らなければ次の本を探せばいいだけだから気楽なところもいい。
詳細は非公開のようですが、無料期間の終了1年後に、Amazonサイトで無料体験の表示が出ていれば、また無料体験できるチャンスがあります。無料体験は年中やっているので気楽に試すことができます。
数千円以上で送料無料・クーポン・キャンペーンがお得
値段を気にせず本を買えるようになっている人にはあまり関係ありませんが、節約したい人なら少し手間を加えるだけでお得な買い物ができるのでおすすめです。
特に古本ですが、数冊買うなら送料が無料になるECサイトのほうが安くなることがあります。ショップによって違いますが、1500円、3000円、5000円などがラインです。
普段から気になる本をリスト化しておいて3冊くらいまとめて買うのがおすすめです。
大手ECサイトはクーポンやキャンペーンをやっています。メルマガなどの通知を使うと知らせてくれます。
先に読まない本を売る
本を買っているとこの先一生読まなそうな本が本棚にたまっていきます。中古市場では毎年価値が下がっていくので売るなら早い方が得です。
- その本を読みたい人の手元へ行き活用されるチャンスがある
- 本棚スペースが空き、新しい本や小物が置ける
- 新しい本を買う資金の足しになる
売ってしまった本が必要になったときは、また買い戻すこともできるので売るリスクは小さいです。
\ 本を売るなら~ブックオフ~♪ /
新本&古本
新品と中古の両方を扱っているECサイト。
\ 元が本屋なので充実のラインナップ、洋書にも強い /
\ 200万点を超える取扱数で他の書店とも連携 /
電子書籍(eBook)
ブラウザ、専用アプリ、PDF、EPUB(イーパブ、電子出版フォーマット)、テキストファイル、画像ファイルなどで読めます。
電子書籍ならではの検索機能やメモ文章追加、しおり(ブックマーク)など紙の本と同じ機能があるサービスもあります。
多くのPDFは固定レイアウトなので見る画面が小さいとスクロールに手間がかかることがあります。
画面が小さいスマホやミニPCなどで読むときは、改行などを自動で行うリフロー型に対応したPDFやEPUBを選ぶと読みやすくなります。
\ 技術書も一番多いAmazonのKindle /
定額の読み放題サービス(※新刊などは対象外)はこちら ⇒ 【PR】Kindle Unlimited 90日間無料
\ 丸善/ジュンク堂/文教堂でも使えるhontoポイント /
\ 業界 第二位の電子書籍サービス /
\ 技術評論社の電子書籍サイト /
\ 国内最大級の総合電子書籍ストア /
\ ITを学ぶ電子書籍ストア /
\ 創作物の総合マーケット /
\ O’Reilly Japanの全書籍がDRM Free/Ebook化 /
\ 翔泳社の通販(IT/開発/マーケティング) /
\ エンジニアとWebディレクターのためのWeb辞書サービス /
\ プログラミング書籍専門の電子店 /
\ オンライン書店|本、雑誌の通販、電子書籍ストア /
電子書籍化のリクエスト
Amazon、楽天、honto などがリクエストの受付を停止しているので業界的に受け付けない流れにあるようです。
技術書が読み放題のサービス(電子書籍)
さしあたり広く浅く学べればいい初心者におすすめなのが電子書籍の読み放題サービスです。
技術書を1冊買うと中古でも1000円以上するので、初心者にとっては自分への投資としても費用対効果が高いお得なサービスになっています。
また、初心者が入門書をたくさん買っても、どうせ読まないでしょうから、初めからいろいろ試し読みできるのは理にかなっています。
最新の人気書籍はまず無理ですが、次のジャンルなら多少人気がない本でも無難に役立つのでおすすめです。
- 入門書
- ハンズオン
- 問題集
- リファレンス
ひとつの入門書で行き詰まっても、ほかの本で同じ部分を探せば違う説明を読めるので問題解決しやすくなり、挫折対策にもなります。



入門書にも善し悪しはあるんだけど、初心者が判断するのは難しいから、あれこれ読める読み放題は便利だよ。
実際どんなものなのかは無料期間があるので試してみて自分の目で確かめるといいです。
基本は月額課金なので1ヵ月だけならそれほどかからないので気になるサービスは試してみるのがおすすめです。
仕方のないことですが、読み放題なので全体的に質はやや控えめでピンキリ感があります。人気の新刊や良書を読むには経済原理に従ってもっとお金をかけないといけません。
| サービス名 | 料金(月額/年額) | 無料期間 | 書籍数/全体 | 技術書の質 | オーディオブック | アプリ | ダウンロード | 動画 | 補足 |
| 【PR】Kindle Unlimited | 月額980円、2ヵ月契約なら499円 | 30日 | 5,000/20,000冊 | 良 | 別サービス | 有/ブラウザ可 | 20冊まで | 無 | 格安キャンペーンあり 最新刊などは読めない |
| 【PR】10xEng(テング) | 月額990円 | 14日 | 不明(300冊?) | 良 | 無 | ブラウザ閲覧のみ | 無 | 無 | ユーザーコミュニティーがある Kidleよりはやや質が高い傾向があるが対応ジャンルが少ない 最新刊などは読めない |
| 【PR】O’Reilly Online Learning | ※ACM会員登録のオプションで年174ドル(約23,000円)(*1) 通常:月49ドル(約6,500円)/年499ドル(約65,000円) | 10日 | 6万冊(英語版を含む総数) | 高 | 有 | 有 | 有 | 有 | 英語版が多い 要英語登録 学習サービスの中に読み放題がある |
| 【PR】IT雑誌&ムック+IT書籍読み放題 | 月930円/年10,680円 | 最大30日(利用開始日で変動) | Web Designing/書籍300冊 | 好み次第 | 無 | 無(P DF/EPUB) | 有 | 有 | 技術系読み物が多い Tポイントが貯まる |
| 【PR】楽天マガジン | 月418円/年3,960円 | 31日 | 40/1200誌 | 好み次第 | 無 | 有 | 有 | 無 | 雑誌専門 楽天ポイントが貯まる |
(*1) 1ドル130円強で計算(※1ドル150円などと円安が進むともっと高くなる)
O’Reilly(オライリー)はハイエンドなサービスですが料金が高く、登録も英語なので敷居が高いです。
年間支払いの場合、追加サービスで約2万3千円になり、月額2千円相当になるので現実的な選択肢に入ってきます。
参考 【サービス復活】年25,000円でACM会員になればO’Reilly本が読み放題になる!!
そもそも雑誌のようなニュースや汎用的な情報は基礎知識の乏しい初心者向きではないので、私の評価は低めになっています。
とはいえ、学習の休憩時間に読むのであればちょうどいいでしょう。
読み放題サービスのおすすめトップ3
- 【PR】Kindle Unlimited
- 【PR】O’Reilly Online Learning
- 【PR】10xEng(テング)
1位 Kindle Unlimited
1位は蔵書が多い Kindle Unlimited です。どのジャンルの本も満遍なくあって、さらに技術書以外の本も読めるのが魅力です。
入門書や問題集、リファレンスなどもそろっているので初心者には特におすすめです。
技術書以外では各ジャンルの名著や人気書籍もあります。むしろこちらのほうが楽しめるかもしれません。
アプリでPC/スマホの両対応で音声読み上げに対応した本ならAudibleのように移動中などに耳で学習することもできます。
(補足:KindleのTTS読み上げ機能はPCアプリのみでスマホでは不可。また読み上げ未対応の本もある。Audibleは人の朗読で倍速再生できる利点がある。)
KindleもAudibleも無料期間が30日あって、その間に解約すればタダで利用できる太っ腹なところも好感が持てます ⇒ 【PR】Kindle Unlimited、【PR】Amazon audible
参考 Kindle Unlimitedで読めるおすすめ本100選【読み放題】
KindleもAudibleも基本料金だけで読み放題・聴き放題の本が楽しめます。
それぞれラインナップが違うので、片方で有料の本がもう片方で追加料金なしで楽しめることがあります。
Amazonのサイトで本を選ぶときに確認できるので、読み放題・聴き放題の本だったら、登録したほうが安上がりになることがあります ⇒ 【PR】Amazon audible
2位 O’Reilly Online Learning
ミドルクラス以降のエンジニア向けだったらこちらのほうが1位です。時間は有限なのでお金をかけてもいいなら質のいいものを選んだ方がいいです。
年間契約でうまく使うと月額2,000円相当で本格的な技術書が読めるのが魅力です。
Kindle はミドルクラス以降のエンジニアが読むには物足りないラインナップですが、オライリーならそんなことはありません。
ミドルクラス以降になるとそれ相応の収入があるはずなので、新刊を普通に買ってもいいです。
ですが、あえて読み放題サービスを使うならこのオライリーは質が高いのでおすすめです。
オライリーにも入門書はあるものの、初心者には少しヘビーなので2位としました。初心者がいきなり年間契約するのもハードルが高いです。
3位 10xEng(テング)
技術系の書籍を扱っている出版社が990円で読み放題サービスを運営してくれているので、基本的には理にかなった有用なサービスになっています。
ベテランエンジニアの考え方を知ることが出来るコミュニティー的なサービスも同じ料金で使えるのでお得感があります。
ただし、蔵書のジャンルにバラつきがあるので、読みたいジャンルの技術書があるかどうか先にチェックしておいたほうがいいです。
Webサービスとしてはベータ版ですし、開発会社ではなく事業会社のサービスですから仕方ないのかもしれませんが、検索機能が使いにくいのが難点です。
単純な書籍のみの検索機能があるといいのですが、ないようです。



ライバルが超大手の Kindle になっちゃうから、がんばって負けないように検索ヒット数を多く見せたいとかいった要望があった結果そうなったんだろう。
それで書籍以外の結果も表示するようになったんだろうな。まあ、ビジネスはいろいろ大変なんだよ。
インターフェースが全体的に独特で分かりにくい傾向があるので使いこなすには慣れが必要です。
こういう改善策をトップエンジニアに相談すればよさそうですが、費用が高くつくので逆に相談しないことでコスパを高めているのかもしれません。
ダウンロードもできないので屋外で読むには向いていません。今後の書籍数の増加やWebサービスとしての品質改善にも期待されます。
雑誌
本としては比較的情報が新しいのがメリットです。読みたい雑誌があればいいですが、学習向きではないので情報収集のひとつと考えればいいでしょう。
趣味で読んでる雑誌があるならついでに使ってもいいくらいのイメージです。技術系の雑誌はそもそも少ないという事情もあります。
注意
ダウンロード不可だとオフライン閲覧できない
毎回オンラインでアクセスしないと読めないサービスもあります。
すべて読めるとは限らない
同じ本のなかでも著作権の関係などで部分的に読めないこともあります。
配信停止
新しく追加される書籍もありますが、配信停止になる書籍もあります。人気作品が一時的に無料化されており、元の有料版に戻るパターンもあります。
価格/仕様/キャンペーンは変ることがある
ネットビジネスは変わりやすい傾向がありますが、読み放題系サービスも同じで変わりやすいです。これは申し訳ないですが、仕方ないので契約前に公式の最新情報をチェックしてください。
ラインナップ
人気書籍は有料だったり、そもそも電子書籍化されておらず、読み放題に含まれないものが多いです。
Kindle読み放題の感想「20冊制限はキツイ」
読み放題サービスは20冊まで自分のライブラリに保存しておける仕様です。
読み放題の本は読み放題ではなくなることがあるので、ライブラリ機能は残しておきたい本を保存しておくという役割になります。
その制限が20冊までなので、新しく気になる本が出てきたときは、別の本を削除して入れ替えるか、タイトルだけメモしておいてライブラリへの追加やダウンロードは我慢するかという選択肢になります。
そこで、あとで読み放題ではなくなりそうなメジャーな本は残して、どうせ読み放題のままだろうという本は削除するというスタイルになってきました。
その結果、Kindleライブラリ以外のテキストやエクセルなどで本を管理したほうが効率がいいことがわかりました。
手間はかかるもののエクセルで管理しておけば、同じ本を2冊買ったり、2回読んだりするのを防げ、ソートもでき、分類にまとめたりもできるので、読書の満足感が高まりそうです。
「それならデータベースを構築すればいいじゃないか」と思ったのですが、すでにスマホアプリがあるので、そちらを使うのもよさそうです。
個人的にはエクセルのほうがカスタマイズできて万能な気がします。
データがバックアップできて、サービス終了したり、個人情報がもれにくいメリットもあります。



エクセルはまさにフレキシブルなデータベースだ。
ファイルを開くのと管理が面倒だから、テキストで一元化するのも悪くないね。
Kindleもそうだけ、Audibleで読書量が何倍も増えちゃったから、うまく管理していきたい。
ちなみに、Kindleアプリのコレクション機能でも本を管理することができます。これはカテゴリー名を付けて管理する機能です。
Audibleにもコレクション機能がありますが、Kindleや普通の本などを横断的に管理するには、やはりエクセルやテキスト、アプリなどが必要です。
Amazonなら利益が拡大できるので、そんな本管理ツールをいつか作ってくれるかもしれません。
読み放題のまとめ
初心者には読み放題はかなりおすすめです。学習はネット記事や動画教材でも出来ますが、短期間で体系的な知識を手に入れるには本が一番効率が良いです。
特に読み放題だと、コスパが良いのと、変な本を間違って買って後悔するリスクがガクンと下がるのでおすすめです。
月契約にしておけば、自分に合わなかったり、使わなくなったときにもすぐに止められます。不安な人もしばらく月契約にしておけば安心でしょう。



本って買っただけで満足して積読になったり、読んでみたらイマイチだったってことがけっこうあるから読み放題もいいね。
オーディオブック
メリットは本を朗読やAI音声で聴けることです。移動や作業中にながら聴きが出来て隙間時間をインプット時間に変えられる優れものです。
耳が慣れると2~3倍速でも聴き取れるようになれば短時間でインプットできるメリットもあります。
技術書だと数が少ないのでIT系ビジネス書などを聴くのに向いています。デメリットは値段が高めなことです。
月々定額で無制限のサブスク型や新刊のみ別料金、単体購入などのタイプがあります。
技術分野では情報鮮度も大切なのでやや向いていないジャンルではあります。
使うなら 【PR】Amazon audible が月1500円で12万冊を買い取りと聴き放題サービスが使えます。
電子書籍が読み放題の 【PR】Kindle Unlimited と同じく、技術書以外のラインナップのほうが楽しめるかもしれません。
もうひとつの候補が 【PR】audiobook.jp です。15万冊を買い取りと月767円、年9,200円で聴き放題などいろいろなプランで聴くことが出来ます。
Audibleの学びは圧倒的(体験談)
「ナレーターが本を読んでいるだけだろう」とたかをくくってましたが、実際に使ってみると想像以上の学びと満足感がえられました。
ネット情報などと違って、書籍化されているものの内容は作者の意見がちゃんと書かれていて、全体的に質が高いです。
その質の高い内容を聴くだけで学べるので簡単にグングンと自己成長できます。
私はビジネス書から脳科学、心理学、哲学、小説などいろいろ聴くので、そのときに関心のある分野のことを聴くだけで学べるのでとても重宝しています。
倍速再生も優秀です。2倍速くらいなら慣れれば十分聴きとれるので、自分で読むよりも早く内容を理解できることもあります。
残念なことにエンジニア向けの技術書は少ないのですが、『世界一流エンジニアの思考法』(牛尾 剛著)のような人気書籍が聴き放題タイトルになることもあります。
プログラム言語の説明を音声でするのは難しいでしょうが、テクニックやマインドなどのポエム系には期待が持てるようになりつつあります。
リーダーなどマネージメント系のキャリアを進んでいる人なら役立つ本がたくさんあるのでおすすめです。
AudibleとKindleは日本語書籍だと連携できない
英語ならWhispersyncで連携できて、Audibleの読み上げ部分をKindleの電子書籍上でハイライトすることができます。英語書籍なら連携できます。
残念ですが2023年6月現在では日本語の書籍は連携に対応していません。
いつか対応されるかもしれませんが、Audibleのメリットは自分で本を見る必要がないことですから、対応の優先度は低いでしょう。
連携には両方買う必要があって値段が高いのもネックです。



マンガが連携すればアニメっぽくなって面白いかもね。
AI音声だとリアリティが出ないし声優を使うと製作費が高くなるから出ないだろうけど。
注意
電子書籍・オーディオブックが読めなくなる恐れ
Amazonアカウント停止で購入した何千冊もの電子書籍がすべて読めなくなったという事件がありました。原因はアマゾンギフトカード関連の規約違反だったそうです。
ダウンロードして保存できるサービスなら安心ですが、それ以外だとアカウント停止で本を読む権利がすべて失われる恐れがあります。
他にもスマホ紛失やPC破損などでも読めなくなるのでパスワードを保存したりその他のリカバリー方法を確認しておくといいです。
PCアプリのキャッシュを削除しよう
AudibleはPCでも聴けます。PC上でスマホアプリを使うこともできました。(その後サービス停止したようですが)
それは、WindowsサブシステムのAndroidエミュレーターで動くAmazon Audibleアプリです。
私がこのアプリでオーディオブックを200冊以上ダウンロードしたところ、キャッシュファイルが30GMにもなって、SSDの容量を圧迫していました。
PC上でファイル検索して削除したのですが、キャッシュファイルを自動で削除する機能がないかもしれません。
自己責任でお願いしますが、PCアプリのキャッシュは自分で削除したほうがいいようです。
キャッシュは1ファイルになっているので、everythingなどのファイラーでファイルをサイズ順で表示すれば見つかるはずです。
削除は少し怖かったですが、今のところ問題ないようです。
また、アプリにも読後の自動削除機能があるので、念のためこれも設定しておいたほうがいいでしょう。



また読みたくなったときに困ると思って、最初は読んだ後も削除してなかったんだ。
でも、読みたい本は大量にあるから同じ本を何度も読む可能性は低いと気付いた。
これはビジネス書で聴いたんだけど、同じのを二回読むより別の本を読んだ方が学びが多いという意見を聞いて、それもそうだと思ったんだ。
それで、AudibleもKindleも図書館みたいに使うことにした。持ってる実物の本は売っちゃおうかなとも思う。
古本・中古
まだエンジニアとして通用するか分からない初心者なら、古書でもいいのでなるべく安く手に入れたいものです。
安くても読めるが、技術書だと問題の答えが書いてあったりするのがデメリットです。
中古も大手はだいたいポイントやクーポンがあってたまにキャンペーンでさらにお得になります。
\ 1500円以上で送料無料! 結果、一番安くなりがち、本を買うなら~♪ /
\ 古本も品ぞろえ豊富でアマギフも使える /
\ 楽天経済圏を生きるならここ、クーポンもお得! /
\ PayPayポイントならここ、ポイントアップキャンペーンを狙おう! /
オークション・フリーマーケット
掘り出し物を探したり、ひたすら最安値を追い求めるのに使えます。
欲しい本のリクエスト
古書のリクエストサービスがあります。
図書館でもリクエストを受け付けているところがあるので利用できます。(※ただし、一定の基準がある)
\ 本がないときはリクエストできる /
図書館なら無料
図書館にもよりますが、エンジニアが読みたいような技術書はあまりないですが、探せばそれなりのものが見つかるといった感じです。
とはいえ、大きな図書館だとネット検索もできるので最初に試すにはちょうどいいです。
ですが、移動時間・交通費がかかり生産性が落ちます。それでも近くに大きな図書館があるなら一度は行ってみるといいです。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 借りるだけなら無料! メジャーな本ならそこそこある 同じジャンルの本を見つけやすい 雰囲気的にモチベ維持しやすい 技術書以外の本も気軽に借りられる ない本は新刊でもリクエストできる 学習スペースやネットが無料で使える図書館もある 積読にならない(返却期日が逆に良い) | 読みたい技術書がない ラインナップが古め 借り返しに時間がかる 交通費/燃料費がかかる 辞書的に手元におけない 書き込めない |



いつか図書館が電子書籍やオーディオブックを貸し出してくれる未来がくるかもね。
本の活用術
エンジニア学習では概念を理解すべし
エンジニアの仕事はネット検索や本で調べられる環境で行うことが多いです。そのため暗記するほど完全に覚えておく必要はありません。
丸暗記よりも、どんな処理や機能があるか、頭の中で体系的に理解することを心がけたほうがいいです。
大枠が頭に入っていれば、細かいところは実装や設計するときに調べられるようになります。まずはその程度の理解で十分でしょう。
逆に暗記が有効なこともあります。
ネット検索やAIプログラミングができない環境での開発や、ある程度自分の専門分野が決まり、その技術ばかり使うようになったときです。
他にはVSCodeやエディターのショートカットなどは、早く覚えてしまったほうが生産性が上がるのでメリットがあります。
意識して覚えたり、メモにまとめて確認できるようにしておくといいです。
必要な本の必要なところだけ読もう
すべての本を読破するほどの時間はありませんし、効率も悪いです。
また、本は古くなっていき、技術は新しいものが出てきます。使わない知識ばかり増えても効率が悪いです。
本を効率的に読むには、本と読む部分を選別する必要があります。そのためには、自分の目的と判断基準をはっきりさせておく必要があります。
たとえば、データベースの処理速度を上げたいなら、速度関連の部分だけ読み、次の本を探すといった読み方がおすすめです。
入門書や資格試験本なども全部が役に立つ内容とは限りません。目的に合わせて必要なところだけ読んで、次の本に進んだ方が賢いです。
Webやシステム開発と同じように、完璧主義は捨てて、優先度の高いものからどんどん取り入れていくイメージです。
ハンズオンはインプットにならないように
ハンズオンの本や動画などは、実際に動くプログラムを作れるので、具体的な仕組みを理解でき、達成感も味わえるのがメリットです。
ただし、完成したプログラムなどはアウトプットよりもインプットに近いので、あまり学習できていないことがあります。
特に自分で考える必要がなく、与えられた答えを確認するようなハンズオンの場合は、思考体験とはなりにくく、インプット学習をしているようなものです。
ハンズオンでも自分で考えて、違うパターンの処理を試したり工夫していけば、思考体験となるアウトプットになります。
ハンズオンではプラモデルを説明書通りに作って満足するようなインプット学習にならないように工夫していきましょう。
最初から問題集に取り組む逆転の発想
プログラム言語などの入門書は、処理の目的などがわかりにくく納得しにくいのが欠点です。
その処理はどんなときに使うべきかと自分で考えて補完しながら学んでいかないと、あまり身に付きません。
ところが、プログラミング経験者ならいざしらず、未経験者が使い道を補完しながら学習することは至難の業です。
せめて演習問題があればマシですが、何もない状態で文法だけを学び続けると退屈で実りのないものになりがちです。
逆に問題集から取り組んで、解くために入門書やネット検索を使えば、課題解決型の高い学習効果が得られます。
答えは見ずに自分の答えを出して、答えを見て納得するくらいがおすすめです。
難易度は高くなりますが、目的を達成するのはエンジニアの仕事と同じスタイルなので、実践的なアウトプット学習ができます。
問題集の解答はコーディングサンプル集
問題と似た処理を作るときには参考コードに使えます。
ブックスタンドで見ながらキー入力
読書台やデータホルダーともいいますが、ハンズオンの本など見ながらキーボードを入力できるので作業効率をアップできます。デスクのスペースが広く使え、ハンズフリーで手も疲れません。
タブレットPCやノートも置けますが、重いものは専用のPCスタンドを買った方がいいです。
金属フレームなどの小型スタンドは携帯に便利ですが、立てかけにくいので平面のものがおすすめです。
開いたページを下からアームなどで固定するタイプが多いですが、本の上が開いてしまうことがあるので左右から固定するタイプのほうがしっかりホールドしやすいです。
下から固定するとアームを上に置くせいで文章が読めない部分ができるのですが、左右から固定すれば全部読めるのもメリットです。
物によりますが、左右で固定するタイプはページをめくるのが少し面倒になる恐れがあるので一長一短ではあります。
本の上部の固定は別にクリップを用意してもいいです。洗濯ばさみだと力が弱いのでイマイチです。
あとは高さが調整できると快適です。外出先で使える折り畳み式も人気です。



毎週、本を何時間も読む読書家の人なら読書時間が快適になって生産性が上がるからブックスタンドをぜひ試してほしい。
スタンディングデスクに本を置いて、ステッパーを踏みつつ、ダンベルで筋トレして運動不足解消なんてこともできるよ。
机のスペースをさらに広く使いたいならアーム式のスタンドもあります。これなら机に置く場所がなくても本が読めます。
アーム式は取り外しが面倒なので持ち運びには向かないので注意してください。



机でご飯を食べたり、ガンプラを作るときに取説を見るのにも役立つよ。
カラーふせんで色分け
小さくて半透明なふせんが便利です。内容の重要度やカテゴリーなどで色分けすれば自分用の本にカスタマイズできます。
本だけでなくノートのカタログなどにもいろいろ使えます。カラーペンで色付けできないときにページ内を強調する使い方もあります。
電子書籍の検索機は便利
便利な逆引きインデックスがついてる本でも、探すのは面倒です。検索機能はやはり便利です。



文明の利器だね。
[コラム] 電子書籍と紙の本はどっちがいいの?
電子書籍には買ったらすぐ読める、場所を取らない、持ち運びが楽、検索できるなどの先進的なメリットがあります。
一方、紙の本のメリットは何かというと、価値が高く感じる、モニターの直接光とは違う反射光で目に優しい、読破後の達成感や所有で満足感が生まれることなどです。
価値が高く感じるのは、日頃、ネットで無料の文字データを流し読みしている現代人にとって、紙に印刷された文字のほうが価値が高いように感じるということです。
価値を高く感じるので読む意欲も高まりやすくなります。
ページをめくるという動作は面倒な部分もありますが、読み進んでいっている感覚を与えてくれます。これも読書意欲や満足感を高める効果があります。
リアルなアクションと本の内容が紐づけられ記憶に残りやすいというメリットもあります。
電子書籍の利便性は認めざるをえないところですが、紙の本にもいろいろな良い点があります。
この記事のテーマである技術書についてですが、時間が経つとどんどん価値が薄れる水物なので、残念ですが長く所有しても本棚を飾る模様のようになってしまいます。
時とともに本はあってもその技術を生かすハードもソフトも消えていってしまう現実もあります。
電子書籍のほうがすぐに手に入って邪魔にもならず、逆引きをしなくても検索できてしまうので、技術書に限っては電子書籍のほうが便利です。
本棚がたくさんあるとか、自分の読書や技術の歴史として残したいといった想いがあるなら取っておいてもいいのですが、古い本は扱いに困りがちです。



読み終わった本をどうすべきかは少し迷うよ。
リファレンスとかは置いといてもいんだけど、一生読みそうもない本を取っておいても仕方ない。
せっかく読んで愛着の生まれた本を捨てるのも気が引けるし、さみしいところだね……
目的別の技術書紹介
私が実際に読んだ本を目的別に紹介しています。追加途中ですが、Kindle本が多く、次に実物の本、Audibleが少々といったラインナップになっていきそうです。
【PR】Kindle Unlimited買う技術書の選び方
技術書はすぐに古くなってしまうので、買わずに Kindle ですませるのがおすすめです。
買うなら、各言語や分野の全体像がつかめる専門書がおすすめです。コーディングルール、デザインパターン、TCP/IPなど技術の変化が遅い分野の本も長く使えるので買っておいてもいいでしょう。
一度は書籍で体系的に学ぶべき
最初に学ぶ言語は人から教わることが多いかもしれません。ですが、エンジニアになると基本独学になります。独学するときは、一度は専門書で体系的に学んでおいたほうがいいです。
仕事では各言語や分野の全体を把握せずに、必要な部分を調べるだけで開発を続けることもできます。ところが、これだと危ない橋を渡っていても気づけず痛い目に遭う恐れがあります。余裕があるときに体系的な知識も学んでおきましょう。
基礎・入門書
『超頻出 ITエンジニア英単語150 Kindle版』松元大地 (著) 形式: Kindle版
スマホでも英単語の意味や使用例がサクッとわかるカジュアルな人気本。プログラミング/Webアプリ/DB/開発関連の用語説明されている。英語をさける人生を送ってきた人や、専門分野が狭い人が学ぶのにちょうどいよい。『続頻出 ITエンジニア英単語105』という本もあるのでこちらも見ておくとよい。内容は少し難しくなている。



記憶は他のものと関連付けたほうが残りやすい。
だから英語の元の意味も合わせて知っておくと、より強く記憶に残っていいよ。



超頻出の本ではイメージで説明しているところがあるんだけど、思ってたのとけっこう違ってた。
若手向けに作った本だそうだから、ジェネレーションギャップかな?
[コラム] 効果的な学習方法とは?
知らない技術を学ぶときは、いきなり問題集やハンズオンの本や動画から始めるのがおすすめです。
理由は記憶に定着しやすい効果的なアウトプット学習になるからです。
わからないことでも自己解決できることが前提になるので、完全な初心者がやるにはハードルが高いので注意してください。
それでも、高い効果が見込めるので、初心者にもチャレンジしてほしい学び方です。
ハンズオンは、答えの通りやるだけだとインプット学習に近いので、工夫して別パターンの処理も試していくといいです。
入門書を読むようなインプット学習は身に付きにくく、その技術をどこで使うのかわかりにくいので、本当は中級者以上でないと学習効率が悪いです。
とはいえ、何も知らないのに問題集など解けないという問題もあるので、入門書から入るのはやはり王道といえます。
忘れやすいものの、広く浅く抜けもれが少ない学習ができます。
いきなり問題集やハンズオンから取り組むデメリットは、知識や技術が偏りやすいことです。
問題集やハンズオンはピンポイント学習になるので網羅性が低いのが弱点です。
また、ハンズオン系はスキルが身についていないのに、実際以上のスキルが身についたと誤解しやすいので気を付けてください。
ハンズオン系で学習すると「これができるようになった!」と感じます。ですが、実際には「このパターンしかできない」状態なので応用が利きにくいす。
弱点はあるものの、問題集のような頭を使って自分で調べながら取り組むアウトプット学習のほうがエンジニア業務の実践にも近く、効率がいいです。
要は、すぐ忘れる入門書よりも、頭を悩ませることで少しでも身に付く問題集のほうが、スキルアップできていいという考え方です。



知らない技術は入門書を2冊も読めばいいかなとも思う。
だけど、一応問題集も見ておくかと思って解いてみると、学習効果が全然違うんだよね。



内容があまり思い出せない入門書と、しっかり身につく問題集なら、問題集のほうがいいでしょうね。



入門書は読むだけで楽だけど、問題集は頭を使う分だけ大変だ。
だけど、そこに高い学習効果があるんだよね。
JavaScript
変数宣言に var を使っている本は、さすがに古いのでさけたほうがいいです。
現在、推奨されていない関数などを学んでしまうリスクがあります。
理論を学ぶだけなら問題ないかもしれませんが、新しいものがあるのでそちらを選んだほうがいいです。
問題集
『脱初心者のための問題集 JavaScript編』 著者:フリーダイバージョージ Kindle版
初心者が初級者になれるくらいのレベルの問題集。解答に実行環境が必要な実践的問題集でアプトプット学習に使え達成感が味わえる(面白い)。設問・ポイント・答えの関係が正しくない問題もあるので、時間をかけて自己解決を目指すより、いったん答えをみたほうがよい。オブジェクト指向やDOMなどは出てこない基礎文法の学習用。
『JavaScript 練習問題100問(タチアナちゃんとstudy) 2024年』 著者:令和情報ファイナンス技術書 Kindle 版
初級~中級者向けの問題集。選択形式や穴埋め式の問題が多く、テストや資格試験に近い。コードは実行したほうがよいが、しなくてもインプット学習ができる。マニアックで、あまり使わなそうな処理も扱っている。全然わからない問題は学習効果が低いので解かなくてもよい。DOMは少し出てくるが、問題はないので知識としてサラッと流し読みするくらいでいいだろう。問題と答えのページが離れていてスマホでは見にくいのでPC閲覧推奨。目次と目次の間に記事があることがあるので1ページずつ見ないと見逃す。表紙のキャラは挿絵的なもので内容とはほぼ関係ない。全体的にザックリした作り。
基礎・入門
『よくわかるJavaScript』高橋 麻奈著 Kindle版
変数宣言に var を使っており、記述はやや古い。しかし、Webページのパーツや動きのある部分が図解されていて初心者が個人サイトを作るときなどには有益な1冊。
『JavaScript 初級者が知るべき39のこと Kindle版』 松元大地 (著)
エンジニアではあるがJavaScriptには詳しくな人向け(要基礎知識)。知らなくてもコーディングはできそうだが、知っておいたほうがいい周辺知識を解説。著者の自説や経験則も含まれているので、1エンジニアの説であり別解釈もあると思っておいた方がよい。
わからない問題はどうすべきか?
問題集の問題で、何を試す問題なのか、何を調べればいいのか、AIに質問する方法すらわからない問題は気にせずスルーしていいです。
原因は問題がおかしい(説明していない技術が必要など)か、自分のスキル不足かのどちらかです。ですが、どちらにしても学習効果が低いので、メモでもしておいてまた後で取り組めばいいです。
問題を解くことは学習によるスキルアップが目的なので、学習効果が低い、つまり学びが少ない問題はいったん後回しすることをおすすめします。
電子書籍は拡大機能を使おう
コードが画像で説明されていると、文字が小さくて読めないことがあります。閲覧アプリなどに拡大機能があれば、使うと便利です。
Kindleだとダブルクリックで画像を選んで、もう一度ダブルクリックすると拡大できる画像があります。
拡大機能がないときはWindowの拡大鏡アプリなどが使えそうですが、単に拡大するだけだと文字がつぶれていて読めないことがあります。